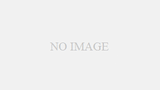こんにちは、あつみです。私には発達障害(凸凹タイプ)の子ども5人を育てています。そのうち4人が不登校&元不登校です。このブログでは、そんな子どもたちを育てていく過程で、私が今まで学んできたことや経験してきたことなどを主にお伝えしていきます。
不登校・発達障害の子が安心して過ごせる場所として、駄菓子屋を経営しています。駄菓子を買うことはもちろん、お絵かきをしたりミニ四駆で遊んだりすることができる駄菓子屋です。こちらに関することもお伝えします。
先日、文部科学省から2024年度の不登校の小中学生の数が発表されました。
その数、なんと35万3,970人。約26人に1人だそうです。
我が家で初めて不登校になったのは、当時小学5年生だった長女。2018年度のことです。その時の不登校の数を調べてみると、その時は16万4,528人だったそう。倍以上になってますね。
あのころに比べると、不登校のための活動をしているところが増えた印象があります。あのころもフリースクールや親の会はありました。私の個人的な感想でしかありませんが、今ほど気軽に行ける感じではなかった気がします。
また、学校の先生をはじめとして、不登校に対する周りの大人たちの対応が変わってきています。これも私の肌感覚でしかありませんが、以前は何がなんでも学校に行かせようとしていたのに、最近は学校に行かないことに寛容になってきた感じです。

(写真はイメージです。写真AC)
ただ、学校に行かないことへの苦しみ・孤独感などは、あのころとあまり変わらないのではないでしょうか。
35万人すべての人ではなくても、たくさんの子どもたちとその保護者がツラい思いをしているんだろうなぁと思います。
我が家は長女に続き、長男、次男、三男も不登校になりました。不登校の親歴8年目です。もうベテランですね🤣
そんなベテランの域に達した(?)私でも不安にかられるときがいまだにあります。
「学校に行かなくて、本当に大丈夫なんだろうか?」「ゲームや動画ばかり見てるのは、本当はダメなんじゃないだろうか?」「このままそっとしておくことが本当に正解なんだろうか?」といまだに思うんです。
また、不登校でありながら活動的にしている子や、積極的に動いている親御さんの話を聞くと、けっこう焦ります。「うちの子はうちの子なりに頑張ってるけど・・・」「私がもっと動かないとダメだったかな・・・」って落ち込んだりします。

(写真はイメージです。写真AC)
先ほどもお伝えしたとおり、不登校のための活動をしているところは増えてきたように思います。気軽に行けそうなところが特に増えた印象です。
私も、「駄菓子屋を通して不登校の子たちのために何か活動ができないか」と模索している内の1人です。
そういった活動の輪がひろがることはとても素晴らしいことだと思います。しかしながら、その活動があることに触れるたびに焦りを感じるのも事実。自分が不登校のための活動をしている立場にいるのにです。
不登校の子育てにおいて『不安・焦り』というのは、どうしても切り離せないものなのかもしれません。
⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️
発達・不登校のための相談室ViA(ウィア)では、発達障害・発達凸凹・不登校などに悩む方たちが少しでも笑顔で過ごせるよう、ご相談を承っています。
ご相談は一対一で行うため、完全予約制です。来談者中心療法を軸に、今抱えている悩みを深く掘り下げ、解決できる道はあるか一緒に考えていきます。
相談室ViAについて、詳しくはこちらから⇩
また、遊べる駄菓子屋CoA(コア)の営業をしています。絵を描いたり、プラモデルの制作をしたりできる駄菓子屋です。
相談室のように深く悩みを掘りさげるというより、ちょっと寄ってみてお菓子買いついでに軽く話すといった感じです。気軽に来てみて下さい。
遊べる駄菓子屋CoAについて、詳しくはこちらから⇩
⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️
最後まで読んでいただき、ありがとうございました😊